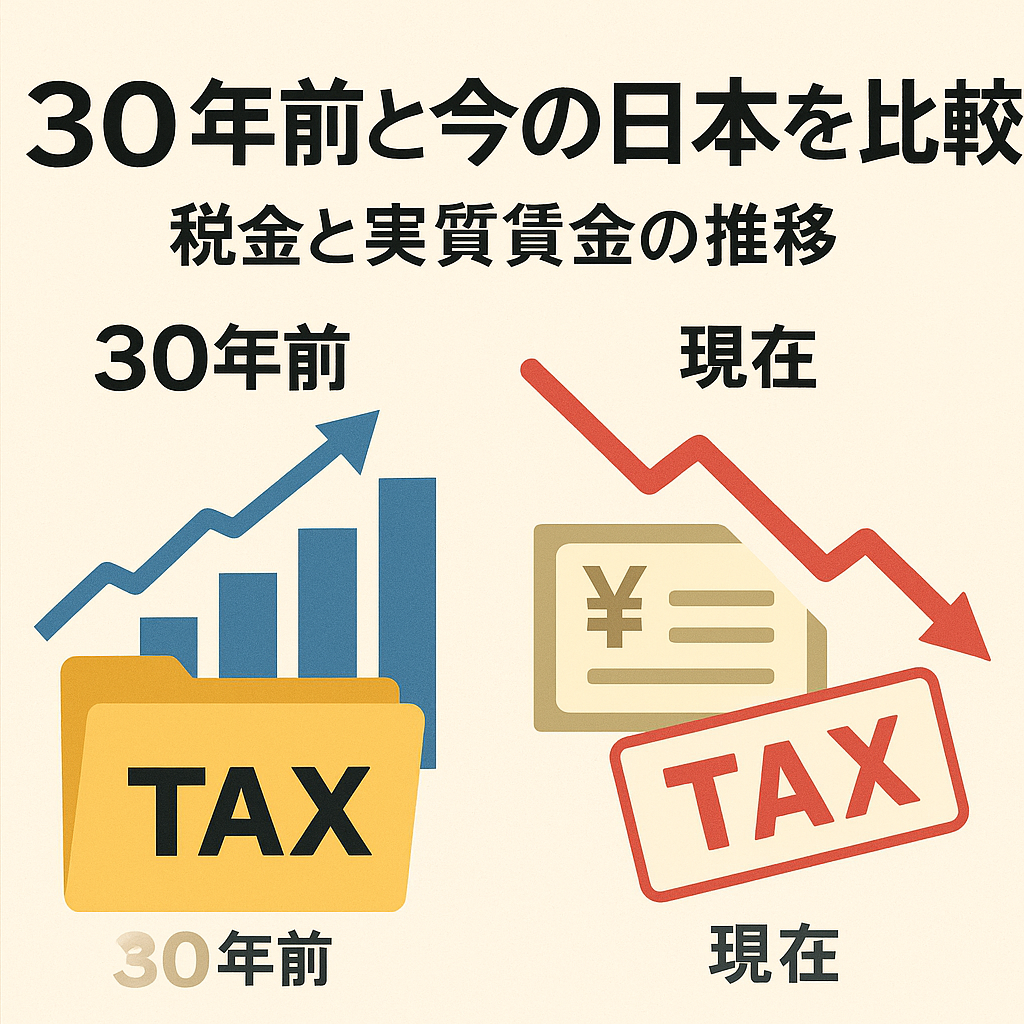はじめに
こんにちはR2-TMです。
「給料は上がらないのに、税金や社会保険料ばかり増えている」――40代のビジネスパーソンなら、一度は感じたことがあるのではないでしょうか。
本記事では、1990年代初頭(約30年前)と現在の日本を「税金」と「実質賃金」の観点から比較し、私たちの生活がどう変化してきたのかを、信頼できる統計と図表をもとに掘り下げます。
1. 平均年収の推移
まずは給与水準を確認してみましょう。
- 1990年の平均給与:425万円
- 2023年の平均給与:458万円
(出典:国税庁「民間給与実態統計調査」)
一見すると名目賃金は増えていますが、増加幅はわずかです。しかも、この間に物価の上昇や税・社会保険料の負担増が進んでおり、実際の生活水準は改善していないのです。

2. 実質賃金の推移
厚生労働省や国際機関の統計によれば、日本の実質賃金は 1997年をピークに下落基調 にあります。
- 1995年から2023年までに実質賃金は 約11%下落 (出典:Wikipedia「失われた30年」)
- IMF報告でも「1995~2021年の日本の実質平均賃金は事実上横ばい」と指摘
つまり、表面的には年収が増えているように見えても、購買力ベースでは明らかに低下しているのです。

3. 消費税の増加
生活コストに直結する消費税の推移を振り返りましょう。
- 1989年:3%で導入
- 1997年:5%
- 2014年:8%
- 2019年:10%
(出典:財務省・国税庁)
例えば、年収500万円の家庭が年間300万円を消費に回すと仮定した場合、
- 1990年(税率3%):約9万円
- 2023年(税率10%):約30万円
実に 20万円以上の差 が生じることになります。

4. 所得税・社会保険料の変化
所得税
1980年代~90年代初頭には最高税率が70%を超える累進課税制度が存在しましたが、その後の税制改革で最高税率は37%まで引き下げられました。
しかし同時に、各種控除の縮小や住民税の改正が行われたため、中間層の負担はむしろ増加傾向にあります。
社会保険料
- 1990年代前半:厚生年金保険料率 ≈ 14%
- 2023年:18.3%(労使折半で約9.15%ずつ)
(出典:厚生労働省「厚生年金保険料率の推移」)
給与からの天引きは年々重くなり、可処分所得は確実に減少しています。
5. 40代ビジネスパーソンの家計シミュレーション
具体例として、年収500万円の会社員をモデルに「手取り」を試算してみます。
- 1990年頃:額面500万円/税・社保 約80万円 → 手取り:約420万円
- 2023年:額面500万円/税・社保 約120万円 → 手取り:約380万円
さらに消費税率の差を考慮すると、同じ年収でも生活できる範囲は大幅に縮小しています。
※実際の負担額は家族構成・控除条件によって変動するため、上記は「目安」です。
6. 日本経済の停滞要因
30年間で見えてきたのは、
- 賃金が横ばい~下落
- 税・社会保険料の増加
- 実質生活水準の低下
という厳しい構図です。その背景には、
- デフレの長期化(1990年代以降)
- 少子高齢化による社会保障費の増大
- 労働生産性の伸び悩み
- グローバル競争での競争力低下
が挙げられます。これらは「失われた30年」と呼ばれる日本経済停滞の本質を示しています。
7. ビジネスパーソンが取るべき対策
- 資産形成(投資):新NISAやiDeCoを活用し、給与以外の収入源を育てる。
- 副業・複業:本業一本に依存せず、スキルを活かした複数収入を確保する。
- 税制優遇の最大活用:住宅ローン控除、生命保険料控除、ふるさと納税などを積極的に使う。
- キャリア形成とスキルアップ:市場価値を高め、停滞した賃金環境でも収入増の余地を作る。
まとめ
30年前と今を比較すると、日本の平均年収は名目上は増加していますが、実質賃金は下落し、税金や社会保険料の負担は増加しています。
つまり、40代ビジネスパーソンにとっては 「可処分所得が減り続ける構造」 が現実となっています。
しかし、現実を正しく理解し、資産形成やキャリア戦略に取り組めば、未来の選択肢を広げることは可能です。
「失われた30年」を嘆くだけでなく、次の30年をどう生き抜くか――いまこそ行動のときです。
出典
- 国税庁「民間給与実態統計調査」(e-Stat)
- 厚生労働省「毎月勤労統計調査(実質賃金)」
- 財務省・国税庁「消費税」
本記事では、できる限り正確な情報をお伝えするよう努めておりますが、掲載データや制度内容には更新や改定があり得ます。また、数字はあくまで一般的な統計に基づいたもので、個々の収入や税負担を保証するものではありません。記事の内容をご自身の判断や行動に活かされる際には、最新の公式資料や専門家の助言をあわせてご参照ください。