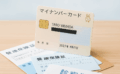説明が上手い人の思考法:上司・部下・顧客に合わせて伝える言葉選び
こんにちはR2-TMです。今回は、前回までの「説明が上手い人・下手な人」シリーズの仕上げとして、上司・部下・顧客という三者それぞれに合わせた“言葉の選び方”を徹底的に掘り下げます。この記事にはプロモーションを含みます。
説明が上手い人は、生まれつき頭の回転が速いわけでも、才能に恵まれているわけでもありません。共通しているのは、「誰に対して、どのような順序で、どのような言葉を使うべきか」を理解していること。言い換えると、説明のテクニックではなく“相手によって言葉を変える”という思考法を持っているのです。
今回の記事では、これまでの「上司編」「部下編」「顧客編」を総合しつつ、説明の本質である“言葉選び”に焦点を当てて整理しました。「どうして説明が伝わらないのか?」「なぜ同じ話でも相手によって反応が違うのか?」という疑問の答えが、この記事を読めば必ず見つかります。
- 【第一章】説明が伝わるかどうかは“言葉選び”で8割決まる
- 【第二章】上司に刺さる言葉選び:曖昧語を排除し、判断材料を提示する
- 【第三章】部下に指示するときの言葉選び:背景・意図・ゴールを明示する
- 【第四章】顧客に刺さる言葉選び:価値を伝える“ベネフィット言葉”に変換する
- 【第五章】上司・部下・顧客の説明を比較すると必要な言葉が明確になる
- 【第六章】説明力を上げる言葉選びの“共通原則”
- 【第七章】関連記事(内部リンク)
- 【第八章】外部リンク(信頼性向上のため)
- 【第九章】雑学:説明と言葉選びに関する豆知識 5選
- 【第十章】楽天ROOMで紹介しているビジネス道具
- 【まとめ】説明力の本質は“相手が理解しやすい言葉を選ぶこと”
【第一章】説明が伝わるかどうかは“言葉選び”で8割決まる
多くの人は「説明=内容」だと思っています。しかし、実は言葉選びのほうが圧倒的に重要。なぜなら、人は説明を“自分のフィルタ”で受け取るからです。
同じ文章でも、上司・部下・顧客では、理解の仕方も、欲しい情報も、判断基準もまったく異なります。つまり、説明の正解は1つではなく、相手によって変わるものなのです。
この視点を持たないまま説明をしてしまうと、たとえば以下のようなミスが起こります。
- 上司に向けて感想や曖昧表現を言ってしまう
- 部下には背景を説明せず「やっといて」と丸投げする
- 顧客には機能を並べてしまいメリットが伝わらない
これらはすべて「言葉選びの失敗」に分類できます。
【第二章】上司に刺さる言葉選び:曖昧語を排除し、判断材料を提示する
まずは上司編の総復習として、上司に効果的に説明するための言葉選びから解説します。
上司が求めているもの:判断材料
上司は、感想ではなく事実 → 解釈 → 根拠 → 対策という“意思決定に必要な情報”を求めています。
そのため、上司の前では次のような言葉はNGです。
- 「たぶん」「なんとなく」
- 「順調だと思います」
- 「大丈夫です、多分」
- 「おそらくはいけるかと」
いずれも「事実ではなく主観」だからです。
上司に刺さる言葉は次のようなものです。
事実:進捗率は85%で、予定比で2日遅れています。
解釈:現状のままだと納期に影響が出る可能性があります。
根拠:外注先A社の遅延が続いており、昨年も同様の事例がありました。
対策:B社へ並行依頼の準備を開始しています。
この形式が最も信頼されやすく、言葉選びの原則も“主観の排除”が徹底されています。
上司に好まれる言葉の例
- 「事実としては〜」
- 「現状は〜です」
- 「理由としては〜が挙げられます」
- 「結論を先に申し上げると〜」
中でも「結論を先に申し上げると」は、上司への説明で使うべき最強フレーズです。
【第三章】部下に指示するときの言葉選び:背景・意図・ゴールを明示する
部下に説明が伝わらない原因の大半は、「言葉が足りていない」か「説明の順序が間違っている」ことです。
説明が下手な管理職は、部下に対して次のような言葉を使いがちです。
- 「これ、やっといて」
- 「前と同じ感じで頼む」
- 「なる早で」
部下は上司の頭の中をすべて把握しているわけではありません。
だからこそ部下には、以下の順序で言葉を選ぶ必要があります。
部下への説明は:背景 → 意図 → ゴール → 手段
例文を見てみましょう。
背景:来月の展示会用の新製品資料が必要だ。
意図:クライアント向けの提案資料に使うためだ。
ゴール:「製品の特徴が一目でわかるA4資料」になっていればOK。
手段:先月の資料を参考にしつつ、写真を差し替えて作成してほしい。
このように「なぜその仕事が必要なのか」を説明されると、部下の理解度と行動の質が大きく変わります。
部下に響く言葉選び例
- 「目的は〜です」
- 「なぜかというと〜だからです」
- 「完成形は〜です」
- 「具体的には〜をしてください」
部下は曖昧な指示より「目的・背景」が明確な指示のほうがやる気になりやすいものです。
【第四章】顧客に刺さる言葉選び:価値を伝える“ベネフィット言葉”に変換する
顧客に説明する際に最もやりがちなミス——
それは、商品の機能を説明しすぎることです。
顧客が本当に知りたいのは、機能そのものではなく、
「それが自分にどんなメリットをもたらすのか?」
つまり“価値”です。
そのため顧客に対しては、機能の説明を「ベネフィット言葉」に変換する必要があります。
機能 → ベネフィット変換例
| 機能 | ベネフィット(価値) |
|---|---|
| バッテリー容量が2倍 | 外出先でも充電を気にせず安心できる |
| 耐久性の高い素材 | 長期間使えて買い替えが不要になる |
| 軽量デザイン | 持ち運びが楽で仕事効率が上がる |
顧客に刺さる言葉選びの例
- 「もし〜でお困りなら、この製品が役に立ちます」
- 「あなたの場合は〜のメリットがあります」
- 「一番大きな価値は〜です」
- 「過去のお客様は〜と評価しています」
顧客にとっての価値を中心に説明できれば、セールストークは劇的に変わります。
【第五章】上司・部下・顧客の説明を比較すると必要な言葉が明確になる
ここで、3者の説明の違いをまとめてみます。
| 相手 | 必要な情報 | 言葉選びのポイント |
|---|---|---|
| 上司 | 判断材料・事実・根拠 | 主観を排除する。「結論→事実→根拠→対策」 |
| 部下 | 目的・背景・完成形 | 「背景→意図→ゴール→手段」の順で説明 |
| 顧客 | 問題解決・メリット | 機能ではなく価値で説明 |
こうして並べてみると、求められている言葉が明確に異なることがわかります。
【第六章】説明力を上げる言葉選びの“共通原則”
① 曖昧語を徹底的に排除する
「なんとなく」「大丈夫だと思います」などの曖昧語は、説明の質を下げる最大の原因です。
② 相手が知りたい順序に合わせる
説明はあなたの頭の中ではなく、相手の頭の中で整理されるべきです。
③ 数字と言葉をセットにする
説得力が大きく上がります。上司だけでなく、顧客にも効果的。
④ ベネフィット変換を癖にする
顧客だけでなく、部下にも効果的です。
⑤ 完成形を言語化する
「どんな状態になればOKか」を必ず言葉で提示する。
【第七章】関連記事(内部リンク)
【第八章】外部リンク(信頼性向上のため)
【第九章】雑学:説明と言葉選びに関する豆知識 5選
- 人は説明の「最初の10秒」で理解するかどうか判断する。
- 数字を含む説明は説得率が40%上がると言われている。
- 部下のモチベーションは“背景説明の有無”で大きく変わる。
- 顧客は「機能」より「自分に関係ある部分」しか覚えていない。
- 説明が上手い人ほど質問の時間を多く取る。
【第十章】楽天ROOMで紹介しているビジネス道具
私が普段使っている説明・仕事効率UPのアイテムは楽天ROOMにまとめています。
【まとめ】説明力の本質は“相手が理解しやすい言葉を選ぶこと”
今回の総集編では、上司・部下・顧客という三者への説明をまとめ、言葉選びの本質に迫りました。
説明の上手い人は、話がうまいのではありません。
言葉の選び方・順序・相手の立場の理解、それらを“相手に合わせて調整できる人”なのです。
今日の仕事から使えるテクニックばかりです。ぜひ現場で試してみてください。
※本記事は、公開されているYouTube動画の内容から着想を得て、私自身の解釈・経験・知識を踏まえて再構成したものです。動画内の具体的な表現・台詞・構成を引用するものではなく、著作権やクリエイターの権利を尊重しながら、テーマを独自に噛み砕いて解説しています。原作動画の制作者さまに深く敬意を表するとともに、本記事は「オマージュ」という形で制作しております。
※本記事は執筆時点の情報に基づいており、内容が後日変更される可能性があります。最新の情報は必ず公式資料等をご確認ください。