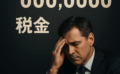【説明が上手い人・下手な人の決定的な違い】上司に刺さる報告術を動画から徹底解説
こんにちはR2-TMです。この記事では、説明が苦手な人が共通して陥りやすい失敗パターンを分析し、動画の内容を参考にしながら「上司への報告が劇的に変わる説明術」をまとめています。この記事にはプロモーションを含みます。
職場で「説明が下手な人」に悩む人は非常に多く、実際に私自身も以前は報告の意図が伝わらず、上司から「結局どういうこと?」と聞き返されることが何度もありました。しかし、説明の原則を理解して習得すると、一気にコミュニケーションが楽になり、仕事の評価も自然に上がっていきます。
説明が上手い人が「なぜ仕事ができて見える」のか
動画では、「説明が上手い人=仕事ができる人」と言われる理由が語られていました。確かに、わかりやすい説明ができる人は、判断が早く、意思決定の質も高い印象があります。しかし、大切なのは説明力は生まれながらの才能ではなく、スキルとして鍛えられるものだという点です。
特に重要なのが、説明は「話し手ではなく聞き手の都合に合わせて構成する」必要があること。動画の中でも、説明が下手な人が共通して持つ特徴として、
- 自分の緊張
- 自分のペース
- 自分が話したいこと
これら「自分」の都合ばかりを優先してしまう点が挙げられていました(03:21)。
逆に説明上手な人は、徹底して「相手のメリット」を頭に置いて説明します。たとえば上司、部下、顧客など、相手が違えば説明の重点も変わる。これを動画では“説明のカスタマイズ”と表現していました(07:03)。
説明下手の典型例:事実と解釈を混ぜる
動画で最も重要なメッセージがここです。上司への説明で怒られる最大原因は、
「事実」と「解釈(自分の考え)」を混ぜて話すこと
でした(12:48)。
これは多くの人が無意識にやっています。
例えば上司にこう言った経験はないでしょうか?
「進捗は順調だと思います。」
これは一見無難ですが、実はかなり危険な報告です。
なぜなら、
- 「順調」というのは事実ではなくあなたの主観
- 上司は具体的な数字・状況が分からないまま判断を迫られる
- 結果的に誤った判断につながる
という大きな問題があるからです(14:05)。
上司は、現状の事実を正確に把握した上で「今どんな判断をするべきか」を決める必要があります(14:56)。つまり、あなたの感想ではなく、正確な現状と、その上での“あなたの考え”が必要なのです。
上司への正しい説明の順番は「事実→解釈」
動画では明確に、上司に説明するときの正しい順序として次を挙げていました(18:37)。
- まず事実(数字・現状)を伝える
- 次に、自分の考え・解釈(対策)を伝える
しかし、事実だけ伝えると上司からこう言われます。
「で、君はどう思うの?」
これが「何も考えていない」と受け取られ、怒られやすい原因になります(17:01)。
そのため、上司への説明には必ず「事実」と「解釈」をセットにする必要があります。
解釈(対策)には必ず「根拠」が必要
動画で強調されていたもう一つのポイントが、
「根拠のない意見は信用されない」(19:55)
という点です。
上司は「なぜそう思うのか」を必ず確認し、根拠のない解釈は「勘で話している」と判断されてしまいます(21:31)。
そこで動画で紹介されていたのが、根拠の優先順位です(20:37)。
【根拠の優先順位】
- 数字(データ)…最も強い
- 仮説(理論的な推測・類似データ)
- 経験談(自分の成功や失敗)
この順番を守って説明すれば、あなたの意見はぐっと説得力が増します。
実際の報告例(正しい構成)
たとえば以下のように説明すれば、上司にとって理解しやすい報告になります。
▼悪い例
「順調だと思います。」
▼良い例
事実:「現在、進捗率は85%で、予定より2日遅れています。」
解釈:「このままだと納期に影響する可能性があります。」
根拠:「遅延要因は外注A社の納品遅れが理由で、過去にも同様の事象がありました。」
対策:「B社にも並行発注することでリスクを軽減できます。」
この形式が、上司から見て最も判断しやすい説明になります。
説明を改善するための「具体的アクション」
動画内容をもとに、私自身の経験も踏まえて“すぐ実践できる改善アクション”を以下にまとめました。
1. 報告前に「これは事実?主観?」と自問する
自分の言葉の中に感想が紛れ込んでいないかチェックするだけで、説明の質は大幅に向上します。
2. 相手が何を知りたがっているかを想像する
上司は“判断材料”を求めています。部下・顧客の場合はまた違う。相手に合わせて説明内容を変える癖をつけると良いです。
3. 事実→解釈→根拠→対策のテンプレを用意する
毎回この順番で話すようにすると、説明が驚くほど整理されます。
4. 数字を必ず盛り込む
説得力が一気に増します。「なんとなく」「だと思う」ではなく、数字やデータを意識的に使う習慣をつけましょう。
ブログ内部リンク
説明力に関連する他の記事も紹介しておきます。
外部リンク
楽天ROOM紹介
私が普段使用しているビジネスアイテムや仕事効率化グッズは、楽天ROOMでも紹介しています。
説明関連の豆知識(雑学)5選
- 人は最初の10秒で話を理解するかどうか決める。
- 数字を含む説明は説得率が40%以上上がるとされる。
- 説明下手な人は「全体→要点」の順番が逆になりがち。
- 上司が最も嫌うのは“曖昧”な報告。
- 説明が上手い人ほど質問の時間を長く取る。
まとめ:説明は才能ではなく、正しい型で誰でも伸びる
今回の動画を参考に記事をまとめましたが、説明が上手くなるために必要なのは“型を知って練習すること”です。
とくに「事実→解釈→根拠→対策」の順序は、どんな仕事でも使える万能フレームです。
説明に悩んでいるなら、今日からぜひ実践してみてください。仕事が驚くほどスムーズに進みます。
※本記事は、公開されているYouTube動画の内容から着想を得て、私自身の解釈・経験・知識を踏まえて再構成したものです。動画内の具体的な表現・台詞・構成を引用するものではなく、著作権やクリエイターの権利を尊重しながら、テーマを独自に噛み砕いて解説しています。原作動画の制作者さまに深く敬意を表するとともに、本記事は「オマージュ」という形で制作しております。
※本記事の内容は執筆時点の情報に基づいており、最新情報と異なる可能性があります。必ず公式情報をご確認ください。